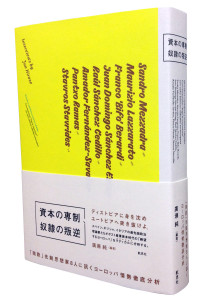オペライズモ、主観性、階級構成(第2部)
Intervista a Gigi Roggero. Operaismo, soggettività e composizione di classe (2) 廣瀬 純
※ジジ・ロッジェーロの略歴などは第1部冒頭を参照。
【承前】

ポストオペライズモが階級の技術的構成と政治的構成とを「ショート」させてしまっているとした上で、君は、この短絡回路を切断するために、社会的労働者の階層化あるいはハイアラーキー化という議論を導入し、現代社会における階級分裂を問題にしている。この議論は今回の君の本『ミリタンシーを讃える――主観性と階級構成についての覚書』の核心のひとつをなしているようにぼくには思える。この点について少し話してもらえないだろうか。
「ハイアラーキー」という語は今日の多くのミリタントあるいはアクティヴィストには耳障りな語となっている。彼らは「水平性」を固く信じているからだ。「ハイアラーキー」は彼らにとっては「よくない」ものなのだ。しかし、ぼくにとって重要なのはよいか悪いかの区別ではなく、何が存在するのかということだ。直接的な与件から出発する必要がある。ハイアラーキーを通じて産み出され、また、ハイアラーキーを絶えず産み出し続けるシステムの内部に水平性など存在し得ない。闘争についてもまた同様に、そのどれもが平等だなどということはあり得ない。個々の闘争によってそのポテンシャリティは異なる。ただしそれは、個々の闘争のポテンシャリティが資本制ハイアラーキー内部で割り振られたそれぞれの「位置」によって決定されるからではない。そうではなく、個々の闘争のポテンシャリティは、そうした「位置」と行動様式とのあいだの関係によって、すなわち、切断と構築の可能性によってこそ決定されるのだ。60年代にオペライスタたちが大衆労働者の政治的中心性を語ったときに問題になっていたのは、まさに、諸々の闘争のあいだにそのように産み出されるハイアラーキーだった。
ぼくは個人的には、ロマーノ・アルクァーティから、システムは構造化されているということ、現実は様々なレヴェルからなるということを教わった。それらのレヴェルがそれぞれいかなる内実をもつのかを理解することがつねに重要だと。水平性は出発点ではなく到達目標なのだ。たとえば「コンリチェールカ」(共同調査)における「コン」(共同)という接頭辞は、ミリタントと労働者とのあいだのイデオロギー的平等を意味するのでは微塵もない。ミリタントはミリタントであり、労働者は労働者であって、それぞれの位置はシステムのなかで、知や知識の所有に照らしてハイアラーキカルに決定されている。「コン」は、ミリタントと労働者とが一緒になってハイアラーキーに対して闘うということを意味するのであり、両者が一緒になってまだ存在しないものを産み出すということ、両者が一緒になって切断をなし新たな組織化過程、新たな主体化過程を産み出すということを意味する。
ネットワークをめぐる今日の議論についても同じことを言わなければならない。インタネットなどについて、ネットワークはそれとして水平性の理念を体現しているといったことがよく言われるが、ここで改めて確認するまでもなく、ネットワークは実際には水平に構成されてなどおらず、むしろ正反対に、徹底的にハイアラーキー化されている。運動の組織化形態についても、たとえばNo Global運動(イタリアでのオルターグローバライゼイション運動)はそのネットワーク型組織化の水平性が語られ賛美すらされたが、どんな組織化形態も水平ではあり得ない。組織化に関して取り組むべき問題は、必然的にハイアラーキカルとならざるを得ない組織化形態がその固定化へと向かい、その内部で諸々の同一性が再生産され続けることになってしまうのをいかに防ぐかという点にこそある。ぼくたちにできるのは、ハイアラーキカルな組織化形態のただなかにありながらなおそれに抗するということであり、ハイアラーキーの外に出ることは端的に言って不可能なのだ。闘争やその組織化形態におけるハイアラーキーを以上のような観点から問題にしなければ、ハイアラーキーがその最悪な形態に陥るという事態を繰り返すことにしかならないだろう。
ここで君の質問に戻りたいと思う。「社会的労働者」は、「大衆労働者」の闘争サイクルが終焉した後、1970年代後半に労働者の新たな中心的形象として見出された。「工場形態」の解体を引き受ける新たな形象、したがって、従来のテイラーシステム型工場にはもはや結びついていない形象、社会的コンテクストそれ自体の工場化としての「社会的工場」をその活動の場とする形象が「社会的労働者」として同定されたのである。社会的労働者は一連の具体的な衝突を通じてその姿を現すことになるわけだが、そうした衝突の象徴とされるのが所謂「イタリアの77年」であり、この出来事においては主として学生たちが、もはや何も保障されていない者として闘争の舞台に登場した。これに対して当時の共産党は、77年刊行のアルベルト・アゾル=ローザ(Alberto Asor Rosa)の有名な本『二つの社会』(Le due società. Ipotesi sulla crisi italiana, Einaudi)での区別に従って言えば、「保障ある社会」の味方につくことで「保障なき社会」を抑圧しようとした。
社会的労働者はたんなる概念などではなく生身の主体だった。目に見える具体的な存在として出現した主体であり、不安定労働者たち、77年の学生たち、社会全体に拡散した工場で闇労働につく若い主体だった。社会的労働者は、抑圧的国家装置との70年代後半の激しいコンフリクトを通じて圧倒的なポテンシャリティを伴って出現したが、概念としてはその後、姿を消すことになる。概念としては失われたが、しかし、問題としては今日もなお微塵も失われていない。ぼくたちはこの問題にいま再び戻らなければならない。先に、ぼくの本が何に異論を唱えているのかを話したが、「情報の短時間性」とでも呼ぶべきものもまた、ぼくの本にとって異論の対象となっている。よく言われることだが、インタネットにおいては短時間のうちに世論がめまぐるしく変化する。今日の話題の中心は明日には忘れられている。時間を長く捉える視座に立脚した議論を回復させなければならない。たとえば大衆労働者は、イタリアでは50年代から60年代にかけて政治的主体として形成されたが、しかし世界的に見た場合にはその時点で初めて出現した主体だとは言えない。大衆労働者は20世紀前半の米国での闘争サイクルにおいてすでに出現していたし、ドイツをはじめとした他の様々な地域でもすでに出現していた。イタリアの例の特徴はその爆発性にあった。必要なのは、「長い歴史」のなかで社会的労働者を再考するということであり、今日の階級構成をめぐる議論のなかで社会的労働者についての言説をいかに生産的に使うかを考え、また、そのことによってたとえば「プレカリアート」概念を乗り越えるといったことだ。
「プレカリアート」概念は実際、「フレキシビリティ」などといったネオリベラリズムの一連の進歩主義的レトリックへの対抗を可能にする概念としてたいへん重要だったが、しかし、ありとあらゆることについてプレカリティが語られる今日、この概念はすでに力を失いつつあるともやはり言わねばならない。すべてとなったものは無に等しいからだ。すべてに等しくプレカリティが見出されるようになると、ハイアラーキーはいかに作動しているのか、何が主体なのか、闘争やコンフリクトの可能性はどこにあるのかといったことが見えなくなってしまう。左派や労組のレトリックには今日「プレカリティに対する闘い」なるものがあり、それ自体としては正しい要求だとも言えるが、そこでプレカリティに対置されるのはきまって正規雇用への回帰、無期限契約で週35時間労働といった意味で理解される「規範的な労働」への回帰だ。しかし、まさにその「規範性」こそ、労働者たちが階級闘争を通じて二度と後戻りできない仕方で粉砕したものではなかったか。労働者たちはテイラーシステム型工場でのサボタージュによって、また、そこからの逃走によって規範性を拒否したのだ。規範性の解体は、しかし、自由世界の構築を導くものではなかった。労働者たちの拒否に対し資本が応答し、規範性の解体に立脚するかたちで、社会全体をひとつの工場として組織することに少なくとも部分的には成功したからだ。プレカリティあるいはフレキシビリティは労働者自身が創出したものであり、階級闘争によってその自律的な形態において導入されたものなのだ。しかし、そのように産み出されたフレキシビリティが敵によって労働力統治の新たな形態のなかに包摂されることになったのである。
60年代には資本による労働力統治のその厳格さを脅かすものとしてあったフレキシビリティが90年代には資本主義的労働政策を救済するための方策へと転じてしまう。その間に力関係が激変したからだ。力関係を問題にすることから始めなければ、この30年間に起きたことも理解できないし、これから起き得ること、これからぼくたち自身がなすべきこともまるで理解できないままにとどまるだろう。「フレキシキュリティ」(flexicurity)などといったように、フレキシビリティの新たなあり方を「提案」したり、「政策」として要求したりするのでは不十分なのだ。「提案」は、先にも述べたが、資本主義側のシンクタンクの仕事であって、ぼくたちのなすべきことではない。ぼくたちにとっての課題は、資本主義に対する抵抗においていかにして新たな厳格さを獲得するか、しかし同時にまた、資本主義の厳格さに対して脅威をなすような新たなフレキシビリティをいかにして獲得するかということにある。ぼくたちは、資本主義がぼくたちにフレキシビリティを求めてくるところでは絶対的に厳格でなければならず、逆にまた、資本主義がぼくたちに厳格さを求めてくるところでは絶対的にフレキシブルでなければならないのだ。
社会的労働者の出現とは、「油で汚れた青い作業着」といった意味では労働者ではもはやないが、しかしなお、敵対的かつ対立的な行動様式という点では依然として労働者にほかならない新たな主体のそれだった。アルクァーティが「新たな労働者性」と定義していたものを今日いかにして考えることができるのか。「労働者性」(オペライエタ)は生産過程のハイアラーキーにおける位置という観点からではなく、あくまでも行動様式と主観性の観点から理解されなければならない。これこそ、ぼくたちが創り出さなければならない中心的結束点であり、それはただ物質的な仕方によってのみ見出すことのできるものなのだ。
問題は、何が進行中であるかということであって、ぼくたちが何を好ましいと考えているかではない。先に、コンリチェールカについて、ミリタントが介入するのはポテンシャリティの見出される場においてであるという話をした。ラニエロ・パンツィエーリ(Raniero Panzieri)はかつて、労働者調査は「熱いうちに行う調査」(コンフリクトをなす運動状況のなかで行う調査)だと言った(«Uso socialista dell’inchiesta operaia», 1965)。今日の問題は、抵抗や拒否といったポテンシャリティがどこにも見当たらないということではなく、ぼくたち自身がそうしたポテンシャリティの高みに達していないということにこそある。ぼくたちには自分たちの不十分さを階級構成の不十分さに投影して自己正当化しようとしているのだ。ぼくたちが力不足なのではなく彼らが闘争しないのだと。闘争がひとつもぼくたちの目に入ってこないのは闘争が存在しないからだといった考えは端的に言って間違っている。50年代の話ばかりをすると当時を神格化しているように聞こえてしまうかもしれないが、しかし、あえて再び50年代のことを例に話すならば、50年代はまさに砂漠の時代だったのだ。たんに政治的な観点からだけでなく、どこを見ればよいのかが誰にもわからなかったという点でもそうだった。オペライズモの独創性はそうした状況のなかでまさに正しい場所に着眼した点にある。彼らの見た場所が正しかったと判明したのはもちろん後になってからのことだ。「オペライスタたちの時代は単純だった、工場に行けば大衆労働者がいたのだから。反対に、今日では事態はずっと複雑になってしまい、どこに行けばよいのかがもはやわからなくなってしまった」といった声がよく聞かれる。この「複雑性」というタームは資本による反革命の時代、80年代のキーワードのひとつだが、これがぼくたちの無能力を正当化するものとなってしまっている。すべてが複雑になってしまったためにもう何もできないというわけだ。しかし、事態が複雑であるからこそいっそうミリタントは頭を使ってその複雑性を引き受け、単純さを以て行動しなければならない。50年代も実際には同様の状況だったのだ。50年代にも敗北感が広がっており、ストライキは無意味だとされ拒否された。しかし、オペライスタたちはストライキのこの拒否こそが新たな闘争なのかもしれない、ストライキを無意味だとして拒否するその振舞いこそが新たなコンフリクトなのかもしれないと考えた。労働者のそうした受け身の姿勢にこそ新たな闘争形態の出現を見なければならないのではないかと。そうしたことが可能となったのは、オペライスタたちが常識に囚われることなしに、また、既存の同一性に拘泥することなしに、ものの見方を一新し得たからであり、マルクス主義の歴史に従わず、マルクスその人から再出発することで、新たな状況のその深い両義性を読むことができたからなのだ。そのようにものの見方を変えることができるかどうかが今日もまた問われているのである。
実際、今日についてもまた、従来の常識に照らせば望ましいとはけっしてみなせないような主体が出現していると言えるかもしれない。ここ数年にイタリアでみられた大きな闘争においても、そこで登場していた主体たちの行動様式はたいへん両義的で、従来のものの見方からすれば好ましい主体などではまるきりなかったと言えるだろう。しかし、主体の行動にはつねに両義性が伴うものなのだ。2013年12月、「フォルコーニ運動」(Movimento dei Forconi. シチリアの農業生産者を中心に2011年に始まった運動)が現行システム全体に異議を唱え、「イタリアを止めろ!」をスローガンに掲げてイタリア各地でデモを組織したが、とりわけトリーノで興味深い展開を見せたこの運動の中心は貧困化した中間層と都市郊外の若者たちだった。左派はこれらの人々をみなファシストだと批判するだけで済ませようとしたが、しかし、彼らは経済危機の直接的なあおりを受けて貧困化した人々だった。農家、商店主、運送業などをはじめとした各セクターの個人自営者などといった典型的な中間層であり、これまで資本主義が彼らに約束してきたものをもはや何も見出すことができなくなった人々だ。これらの人々の振舞いは左派の理解の枠内には収まらないものであり、それゆえに左派は彼らをファシストとみなすことしかできなかった。1962年にトリーノの憲法広場に溢れ出した大衆労働者がたんなる扇動者としか受けとめられなかったのと同じだ。
ここ数ヶ月、イタリアでは銀行救済が大きな問題となっている。救済の対象となっているのはエトルリア・ラツィオ銀行、フェラーラ貯蓄銀行など、すでにイタリア銀行の指導下におかれていた中小地銀4行だが、とりわけエトルリア・ラツィオ銀行は、レンツィ政権の閣僚マリア=エレナ・ボスキの父親が副社長を務めていたという点でも、民主党と近い銀行だ。今年の1月1日からEUでは「ベイルイン」(bail in)による銀行破綻処理が義務化されたのだが、預金者に犠牲を強いることになるベイルインの適用を避けるとの理由からレンツィ政権は、昨年11月23日、株券と債券とを無効にした上で不足分を破綻処理基金(銀行間準備金)で補うという仕方でこれらの銀行の救済を行った。しかし、多くの預金者(13万世帯)は実際にはその預金で劣後債(ジュニア債)を購入していたために、その無効化によって貯蓄のすべてを失い、自殺者まで出ることとなり、レンツィ政権はイタリア住民からの激しい憎悪にさらされることになった。ベイルインの事実上の事前適用と言えるこの銀行救済によって蓄えを失ったのはとりわけ中間層、労働者層であり、彼らはこれまでずっと働いてきて、福祉国会体制が崩壊し年金制度も不安定化しているなかでなお自力で将来の安定を確保するために、銀行を信頼して収入の一部を預金し、銀行員の勧めに従ってそれを運用に充ててきた人々だ。銀行が倒産することなど想像すらしていなかった彼らは、しかし、老後のために一生かかって貯めたお金のすべてが突然、一瞬にして消えてなくなるのを目の当たりにしたのであり、自殺した初老の男性は10万ユーロもの大金を失った。
ぼくたちは今回の銀行救済で犠牲になった預金者たちへのインタヴューを行い、その記事をCommonwareのサイトに掲載している(«Banche salvate, risparmiatori azzerati», 24 Marzo 2016)。インタヴューのなかで彼らはそれぞれ、銀行とのそれまでの付き合いがどのようなものだったか、どのような経緯で債券を買うようになったかを語り、また、お金を取り戻すために今後もありとあらゆる行動をするつもりがあるといったことを話している。彼らから話を聞くなかで、しかし、明確になった重要な点がひとつある。敵対性やコンフリクトの主体は今日では左派の主体ではないという点だ。人々は今日、銀行に対する彼らのこれまでの信頼、代表性の危機という文脈においてはより一般的に、システム全体に対する彼らのこれまでの信頼を断ち切りつつあるが、その切断を具体的に組織し目に見えるものとしているのは五つ星運動(たいへん両義的ではあるが今日とりわけ注目に値する組織)であり、北部同盟(ファシストでありレイシストである右派組織)なのだ。人々が五つ星運動や北部同盟を選択するのは、しかし、それらの組織の掲げるイデオロギーに賛同してのことでは必ずしもなく、何よりもまず、自分たちのおかれている条件のその物質性に立脚してのこと、すなわち、中間層の崩壊、将来設計の破綻、約束された未来の消失、信頼メカニズムの切断といった今日の物質的条件に立脚してのことであり、また、五つ星運動や北部同盟が彼らを引きつけるのは、そうした組織の所謂ポピュリズムが敵を同定し名指す力を有しているからなのだ。もちろん、そこで同定される「敵」が偽のものであるのは言うまでもない。北部同盟は移民を「敵」として同定している。マルクスの言うような意味でのミスティフィケイションがここに見られるのは疑いようがない。しかしこれに対して左派は何をしているのか。「敵」を移民に求めるのは良識に反すると反論するだけだ。今日の左派政治は良識を振りかざすだけのものとなってしまっているのであり、ぼくからすれば、いつの時代にも増して今日ほどそのような左派政治の打倒が急がれることはない。必要なのは社会的コンテクストの二極化であり、二極化を政治的に組織することだからだ。ぼくたち自身もまた、二極化を政治的に創り出す力をもたなければならない。ぼくたちが敵として同定すべき階層は、端的に言えば、金融資本のそれであり、もちろん、この階層はあくまでも名も姓もある特定の具体的な人々から構成されているもので、抽象的な存在では些かもない。そのようにして具体的な敵を同定し、階層化を創り出す限りで初めて、ぼくたちはポピュリズムとそのミスティフィケイションとを退けることができるのだ。
ぼくたちは、両義性に塗れた人々の行動様式をそれでもしっかりと読解し得るよう、自分たちのものの見方を一新し、その上でさらに、その両義的で不純で薄汚れた主体たちを組織化へと導かなければならない。労働が社会化された今日、新たなハイアラーキーをどこに読みにいけばよいのかという問題は確かに難問だ。労働の空間と時間とはテイラーシステム型工場とフォーディム社会とからなる社会においては比較的はっきりと限定されていたが、今日では、そうした空間性も時間性も粉砕されてしまっている。しかし「粉砕された」というのはすべてが等しくなり、いかなる区別も不可能になってしまったということでは些かもない。メトロポリス全体が生産過程に呑み込まれてしまったという認識は正しい。しかしそう認識するだけでは不十分なのだ。メトロポリスは平坦なフローなどではない。メトロポリスは、90年代にネオリベラル派が唱えたような「フラット・ワールド」などでは微塵もなく、ハイアラーキーをその新たな形態において生きている。金融化は確かにフロー化のことでもあるだろう。しかし、そのようにフローが創り出されるにはどこかに具体的に蛇口がなければならない。そうした蛇口はどこにあるのか。そうした蛇口の在処を具体的に同定し、そこを攻撃の対象としなければならないのだ。
【第3部に続く】